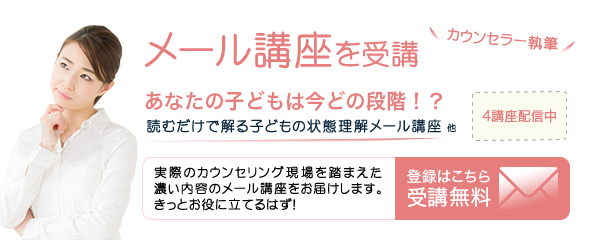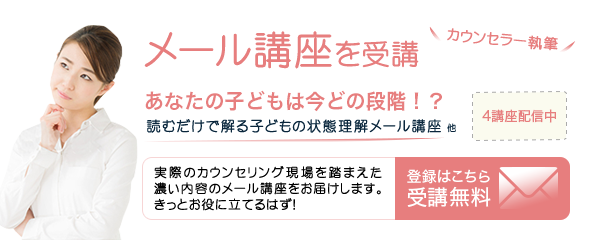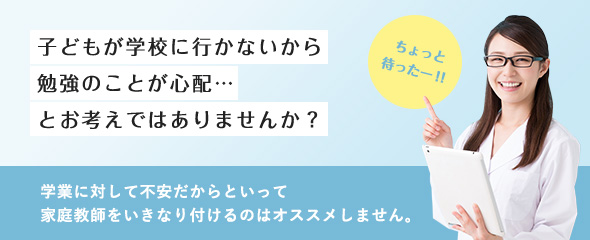子どもの発達段階と不登校との関係①~小学校低学年~
こんにちは。不登校支援センター横浜支部カウンセラーの本沢裕太です。
今回は、子どもの発達という側面から不登校との関係について考えてみたいと思います。
子どもの発達と不登校との関係
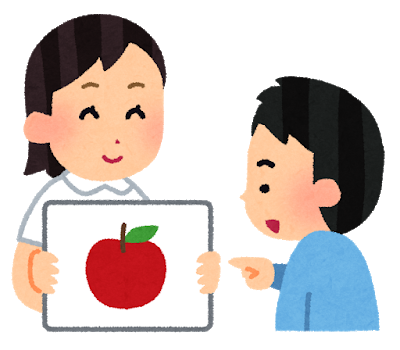
まず、子どもが自立した大人へと成長する過程は、いくつかの段階に分けられ、その発達段階ごとに特徴があります。
もちろん個人差はありますが、それぞれの発達段階での特徴を踏まえた成長を達成する事で、その後も継続性のある成長が期待されます。
逆に、段階ごとの成長を上手く得られなかった際に、
- 劣等感が強まったり・・・
- 社会から拒絶された感情を抱いてしまったり・・・
- 人間関係の構築が苦手になる・・・
など、その後の発達段階での成長が困難になる場合があります。
そのため、子どもの成長にとっての基盤である「家庭」が、心安らぐ場所になっているかを見つめ直す目安の一つにして頂ければ幸いです。
最近、相談件数が増えてきている小学生の発達段階について
まず、小学3年生までの低学年と4年生以降の高学年とに分けて考えます。
なぜかというと、低学年と高学年で求められるものも異なってくるからです。
◆小学3年生までの学童期
この時期の特徴の一つとして、学校での生活の中で知識や技能を身につけ、仲間との集団関係を育成する「勤勉さ」が求められます。
この「勤勉さ」とは、単に勉強面の事ではなく、
- 物事を完成させる力を得る、完成させる喜びを感じる
- 周囲からの承認、自己の有能感や自尊心が得られる
ための行動になります。

この時期の善悪の判断基準や規律意識は、「親や先生に言われた通りに行動する事が正しく、罰を受けないために言われた通りにする」という所が基盤となっている様子が見受けられます。
そういった中で、集団や社会でのルールを守る態度が養われていくのです。
そのため、
- 自分は言われた通りに出来ない
- 自分は周囲から承認されない
といった状況が増えてくると、強い劣等感を感じてしまいます。
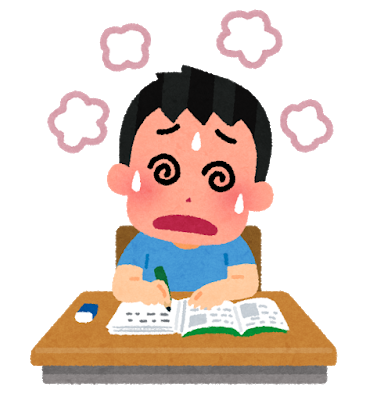
ですので、周囲との関わりの中で
- 自分の長所
- 成長した点
- その他、自分の様々な側面
などに気付き、自己理解を深められる様になる事が望ましいと考えられます。
また、言葉での理解については発達途中といえるので、言葉でのコミュニケーションでの相互理解は、期待しない方が良いかと思います。
- 良い所を直接伝えてあげる事
- 動作や表情などの非言語なコミュニケーションから受け取った自己表現を言葉で伝え返してあげる事
- 怒鳴る、大声で怒るのではなく、何に対してどれくらい怒っているのかを分かりやすく伝えてあげる。(場合によっては、数字や絵などを使う事も有効かと思います)
- こちら側が、今どんな気持ちでどうして欲しいか
という事を、穏やかに伝えてあげる方が理解しやすく、どうするべきかを主体的に考える様になります。
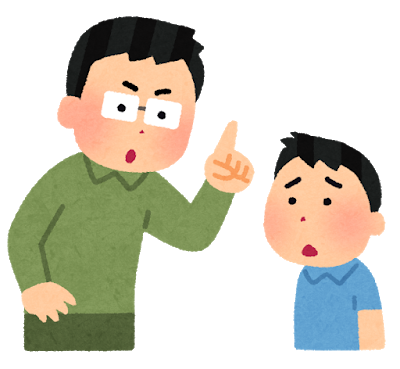
事例の紹介
小学3年生の男の子のA君は、学業面での苦手意識や劣等感が強く出た事が不登校のきっかけとなりました。
親御さんの話では、音楽や図工などの授業が嫌だと言いだしたとの事でした。1、2年生の時には、そんな発言もなく楽しそうに話してくれる事もあったそうです。
「何で急に嫌になっちゃったのかな・・・」と親御さんも心配されておりました。
話を聞いていくと、その子どもは色々な事に対して、一生懸命取り組みたい、周りからも承認される自分でいたい、という思いがあるのが分かってきました。
3年生になり、新たに社会・理科という科目が増えた事や他の科目も難易度が増した事で、今までよりも学習量が求められたり、
- 「やっても思うようにできない」
- 「親や先生の期待に応えられない」
というもどかしさを感じて、自分の中でいっぱいいっぱいになってしまっている様でした。
その間、親御さんや周りの大人がどの様な関わり方をしていたかというと、
「出来ている所を承認する」
という事をひたすら意識して声掛けをしていたそうです。
当初の親御さんや先生の声掛けとしては、
- 宿題が全部終わらなくても良いから、とりあえず学校には行きなさい(来なさい)
- 誰だって得意不得意があるんだから、気にしなくて良いよ
- 友達と楽しく遊べれば、それで良いじゃない
- 途中からでも行ったら? 嫌になったら帰ってくれば良いじゃない
などだったそうです。
それでも全く学校に足が向かない子どもの様子を見て、困り果てているといった状況で相談に来られました。

上記の声掛けの一体何がいけなかったのでしょうか?
この声掛けは、主体が親御さん(先生)であり、
親御さんが、子どもに学校に行ってもらいたい
親御さん(先生)の不安を減らしたい(失くしたい)
といった目的が強く出ている様に感じます。
その時の子どもからすると
- 自分が嫌だと訴えている事を軽んじて受け取られた。
- 自分の気持ちは無視して、正論を押し付けられている。
- どうせ自分は学校にも行ってないし、何を言っても聞いてもらえないんだ。
- 話すのが嫌になり避ける様になる。
と、ますます自分のことも、相手のことも肯定出来なくなっていました。
この悪循環が続くと、学校の話題以外のコミュニケーションも困難になってきます。
出来ている事を承認するとは?
「学校に行っていない」という事を、善と捉えるのか悪と捉えるのかは、人によって捉え方が全く違ってくるかと思います。
そして、学校に行っていない子が、その事を善しと感じているかというと、必ずしもそうではありません。
このテーマは、親御さんからもよく質問にあがりますが、不登校支援センターでは
「善悪の判断を、周りがしない」
という考え方でいます。

なぜなら、「学校には行くべきだ」という考えも、「そんなに嫌なら無理して行かなくて良いのでは」という考えも、どちらも間違っているとは言えないからです。
大切なのは、周りの大人がどう捉えているか、よりも、当の本人がどう感じているか、ではないでしょうか。
なので、出来ている事を承認しようとする際、「学校」というテーマから一度離れた方がしやすい場合が多いです。
例えば、A君の場合ですと、
- 起床時間(就寝時間)を自分で決め、守ろうという努力が見えた
- 食わず嫌いなものを、挑戦して食べてみた
- 今までなかなかゲームが止められなかったが、自分で終わりを決められた
- 出来ないと思う事をすぐに諦めてしまうのではなく、粘り強さが少し見えた
- 親御さんのお手伝いを率先してやる時があった
- 思い通りにならない時でも、感情的にならずに気持ちを切り替えられた
- つまらなそうにしている友達を見て、自分から声を掛けられた
- 自分から「○○したい(してみる)」という発言が増えた
こんな変化が見られ、親御さんもそれに気付き声を掛けておられました。

こういった「学校の話以外の時に、ちゃんと出来ている事、やろうとしている事を承認してくれるんだ」という体験が積み重なってきて、学校の話が建設的に出来る様になりました。
- 運動会はどうするか
- お楽しみ会はどうするか
- PTA主催のバザーはどうするか
- 地域のお祭りはどうするか
などの行事ごとも、親子で話し合い、どうするのかをA君が自分で決められる様になっていきました。
それから、
- 放課後、先生に会いにいってみる
- 給食の時間だけ行ってみる
- この授業にだけ行ってみる
- この日だけ行ってみる
- この日とこの日に行ってみる
と登校頻度が増えつつあります。
その後のA君ですが、お友達から誘われた様で、音楽と図工の授業にも行ってみようかなという話も出ておりました。
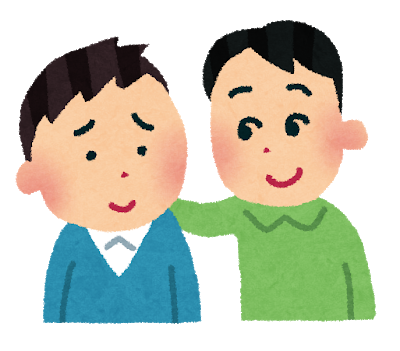
最後に
- なかなか学校の事を切り離して、子どもの事を見れない
- 分かっているけど、出来ている事への声掛けが難しい
とお感じになる親御さんもいらっしゃるかと思いますが、ご自身を責める必要はございません。
それは「なぜそう思うのか」「なぜそう感じるのか」という親御さんの自己理解を深めるきっかけになるかも知れないからです。
そして、自己理解を深めるという事は、
- 些細な事でイライラしなくなる
- 周りの人を受け入れる寛容さが身に付く
- 本当はどうしたいんだろう、どうなりたいんだろうという気持ちに気付く
- 自分に正直になる
といった事へも繋がるチャンスでもあるのです。
せっかくのチャンスを、ネガティブな感情に捉われてしまうだけでは、もったいないと思います。
そうならない様、是非、賢明な判断をしてください。

次回は、小学校高学年の発達段階についてお伝えしたいと思います。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
関連ワード: 低学年 , 判断 , 劣等感 , 動作 , 勤勉さ , 周囲からの承認 , 善悪 , 喜び , 子どもの発達 , 完成させる力 , 小学3年生 , 小学生 , 成長 , 成長過程 , 拒絶感 , 有能感 , 特徴 , 自尊心 , 自己理解 , 表情 , 規律意識 , 非言語