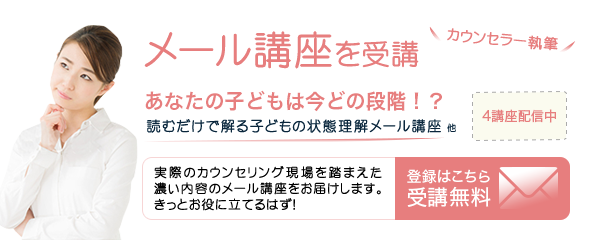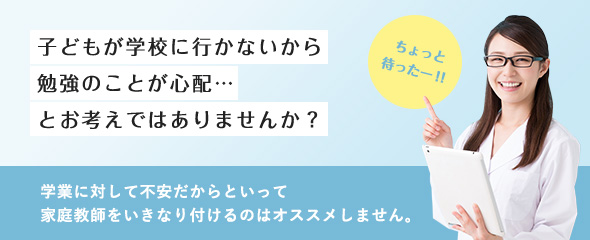なぜ宮城県の不登校生徒数が全国1位なのか?~県の公式見解と対策から考察~
こんにちは。不登校支援センター仙台支部の上原です。
今回は不登校支援センター仙台支部の拠点である、宮城県の不登校事情について取り上げます。
皆さんもご存知かもしれませんが、文部科学省の調査によると、実は宮城県は全国でもトップレベルに不登校生徒数が多い県であるということが判明しています。特に平成26年の調査では、宮城県の中学1年生の不登校生徒数が日本で1番多かったんです。
なぜ宮城県は不登校生徒数ワースト1位になってしまったのでしょうか?
宮城県の公式見解と共に考えてみたいと思います。
 平成27年3月に宮城県教育委員会が「中1不登校の解消に向けて」という冊子を作成しています。冊子には
平成27年3月に宮城県教育委員会が「中1不登校の解消に向けて」という冊子を作成しています。冊子には

 このように、不登校生徒ごとに個別で行っている、不登校支援センターと教職員の方々の連携を、学校全体としても進められたら良いのかもしれません。
しかし私たちのような民間の支援団体には相談しにくい、といった面が学校側にはあるのかもしれませんね。不登校支援センターが実施し、取り組んでいる生徒向けのセルフケア講座や教職員向けセミナーなどは、宮城県の学校ではまだあまり利用されていない現状があります。
外部機関との連携という部分が改善されていくと、宮城県の不登校問題の現状が改善していく可能性もあるかもしれません。
このように、不登校生徒ごとに個別で行っている、不登校支援センターと教職員の方々の連携を、学校全体としても進められたら良いのかもしれません。
しかし私たちのような民間の支援団体には相談しにくい、といった面が学校側にはあるのかもしれませんね。不登校支援センターが実施し、取り組んでいる生徒向けのセルフケア講座や教職員向けセミナーなどは、宮城県の学校ではまだあまり利用されていない現状があります。
外部機関との連携という部分が改善されていくと、宮城県の不登校問題の現状が改善していく可能性もあるかもしれません。

不登校になったきっかけはなんだろう?
 平成27年3月に宮城県教育委員会が「中1不登校の解消に向けて」という冊子を作成しています。冊子には
平成27年3月に宮城県教育委員会が「中1不登校の解消に向けて」という冊子を作成しています。冊子には
- 宮城県が取り組んでいる不登校対策支援モデル
- 学校や生徒に対して実施した不登校の現状調査におけるアンケートの結果や考察
- 不登校改善モデル 等
宮城県が行っている、不登校の未然防止策と初期対応とは?
宮城県は県内の小中学校に不登校の未然防止と初期対応に関してのアンケートを実施しています。具体的に宮城県の小中学校ではどのような不登校の未然防止策と初期対応を実施しているのでしょうか?【未然防止策は?】
不登校生徒数が5人以上の学校と、そうでない学校のアンケートの回答を平均値と比較し、その差に着目し分析・考察が行われています。特に差が大きかったのは「子ども全員への声掛け」を実施しているという項目です。実施している割合が高いのは不登校生徒数が少ない学校であり、ここが不登校数が5人以上の学校とそうでない学校との一番の違いと考えられます。 宮城県教育委員会では、「分かる授業作り」を重要な未然防止策のひとつに位置付けています。それは、課題の明確化や、成功体験の創出によって生徒ひとりひとりの自己有用感や自己肯定感を育む教育を通し、魅力ある学校づくりをして不登校を防ぐという教育体制を表わします。また、今後の課題は「小・中学校の交流や連携」とされています。
【初期対応は?】
初期対応として行われているのは- 教室以外での情報収集
- SC(スクールカウンセラー)、SSW(スクールソーシャルワーカー)との連携
- 管理職、主任、担任への報告体制
- 子どもとのふれあいの時間作り
- 子どものサインを見逃さないようにする
- 気になる変化を保護者と共有する
学校の不登校対策の現実は・・・
冊子には教育委員会からの- 〇月~〇月には〇〇に配慮して対応する
- 不登校が発生したら1日目2日目には〇〇の対応する
では、不登校問題への対応策をどのくらい学校側は実行できているのでしょうか?
実行するには、「現実的に実行できる内容なのか」が大きなポイントであると考えられます。少なくともここで書かれているような動きをしている学校は少ないように私は感じます。 学校の教職員の方々は膨大な量の仕事をしており「人手不足による多忙で、そこまでの細やかな対応をする時間が取れない・・・」という話を、実際に私は耳にしたことがあります。現実的に実行できる体制作りが必要とされるのかもしれません。学校と外部機関との連携が不足している?
アンケート結果の中で、不登校支援センターのカウンセラーである私としては気になる項目が1つありました。「学校が不登校生徒への対応のために連携した外部機関」という項目です。 学校側が不登校問題対策として連携した外部機関として、割合が高いものは- 教育委員会
- 児童相談所
- 病院
 このように、不登校生徒ごとに個別で行っている、不登校支援センターと教職員の方々の連携を、学校全体としても進められたら良いのかもしれません。
しかし私たちのような民間の支援団体には相談しにくい、といった面が学校側にはあるのかもしれませんね。不登校支援センターが実施し、取り組んでいる生徒向けのセルフケア講座や教職員向けセミナーなどは、宮城県の学校ではまだあまり利用されていない現状があります。
外部機関との連携という部分が改善されていくと、宮城県の不登校問題の現状が改善していく可能性もあるかもしれません。
このように、不登校生徒ごとに個別で行っている、不登校支援センターと教職員の方々の連携を、学校全体としても進められたら良いのかもしれません。
しかし私たちのような民間の支援団体には相談しにくい、といった面が学校側にはあるのかもしれませんね。不登校支援センターが実施し、取り組んでいる生徒向けのセルフケア講座や教職員向けセミナーなどは、宮城県の学校ではまだあまり利用されていない現状があります。
外部機関との連携という部分が改善されていくと、宮城県の不登校問題の現状が改善していく可能性もあるかもしれません。
宮城県の不登校事情の今後は?
今回は、宮城県の現在の不登校問題の状況や取り組みなどについてまとめてみました。今後、宮城県の不登校事情はどうなっていくのでしょうか。 残念なことに平成30年の現在でも宮城県の不登校生徒数は全国でもトップクラスのままです。課題として挙げられたものへの取り組みもまだこれからといったところでしょうか。 県としての取り組みや課題に私達も理解を示しながら、何よりも子ども自身の力を伸ばせるような対応をしていきたいですね。 それではまた。
関連ワード: セルフケア講座 , 不登校のきっかけ , 不登校の原因 , 不登校事情 , 不登校専門 , 不登校支援センター仙台支部 , 中1の不登校 , 中1不登校の解消に向けて , 全国ワースト1位 , 外部機関との連携 , 学校との連携 , 学校と外部機関との連携 , 学校の対応 , 学校側の不登校対策 , 宮城県 , 宮城県不登校 , 宮城県教育委員会 , 教師の多忙 , 教職員セミナー