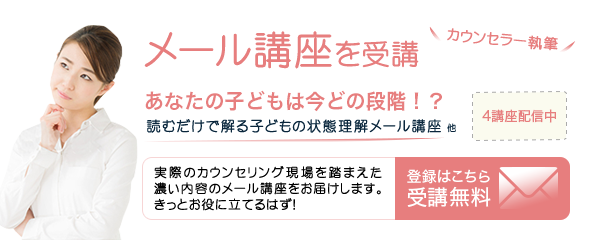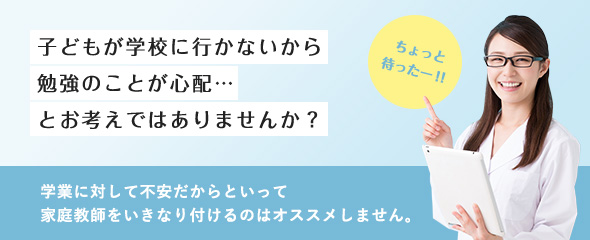子どもが自分で動かないのはなぜ?
こんにちは。不登校支援センター東京支部の小川泰一です。
夏休みが明けて、2学期が始まりましたね。2学期になると、学校行事が増えたり、学習内容も難しくなったりなど、何かと親御さんのサポートが必要な機会も増えてくることと思います。

そんな中でよく伺うのが、「子どもが自分で動かない!」というお悩みです。
動かない子どもにイライラ…

「なるべく子どもに任せたいけど、言わないと動かない…」
「やることを決めてあげないと、動けない…」
「結局最後に焦るパターン…いいかげん学んでくれ…」
そんな気持ちもあり、子どもに声をかけるも効果はいまひとつ…そういった親御さんも多いもしれませんね。
なぜ子どもは動かない?

ここからは、子どもが動かない理由を探っていきたいと思います。
① 誰かに動かされている状況になっている
子どもに限らず、多くの人は『自分がやろう』と思ったことをしています。
自分がしたいことや、する必要があったりすることは、その最たるものですね。逆にする必要がなかったり、意味がないことは、よほどの理由がない限り行動しないことも多いかと思います。
きっかけは他人からの声がけだったとしても、誰かに「させられる」のではなく、自分で納得することで自ら行動するようになるのです。
試しに、親御さんからお子さんへの声がけを控えた時、「子どもが何をしているか、それをどのようにしているか?」を観察してみてください。
楽しむことが好きなのか、達成感を求めてるのか、誰かの役に立ちたいのか…そういった子どもの性格の傾向だけを見ても、子どもにとって何がモチベーションになるかが見えてくるかもしれません。
② やるべきことの量に打ちひしがれている
やるべきことが多く本人の行動できる限界の量を超えてしまうと、何から手をつければいいか考えることも億劫になり、その場をしのぐことで精一杯になってしまいます。
そんな時は、
- 自分にとって負担になっているものは何なのか?
- どうすれば自分は楽しく過ごせるか?
- 量やペースは自分にとって適当か?
などを、親御さんと一緒に見直してみてください。そのあたりの取り組み方が変わるだけでも、お子さんの心身の負担感は、軽減するかもしれません。
③ 子どもにとって、優先順位が低い(=必要性が低い)行動である
この場合、該当の行動に対しての優先順位を上げることが必要になります。
もしお子さんが、今やるべきことより気になっていることがあれば、まずはそれを解消することが先かもしれません。
また、達成感を感じることがモチベーションになるお子さんであれば、スモールステップを重ね、達成感を積み重ねていくことで、自然と優先順位が上がっていくかもしれません。
子どもの中の優先順位を上げるためにはどうするか?そういった視点から働きかけてみていただければと思います。
今だからこそ…

以上、子どもが動かない理由を見てきました。今、お子さんがどういった状態で、どんな働きかけが必要なのか?お子さんがまだまだ成長途中の今だからこそ、この機会にぜひ一緒に考えていきましょう。
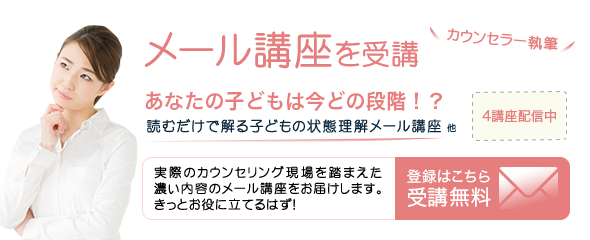

関連ワード: 主体性を育てる , 勉強 , 動かない子ども , 子どもの主体性 , 子どもの心理 , 子ども自ら動く , 積極的に行動する , 自主的な行動 , 自主的な選択 , 親子関係