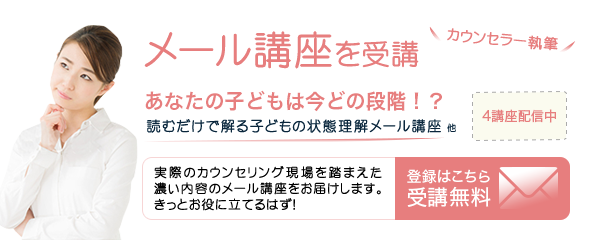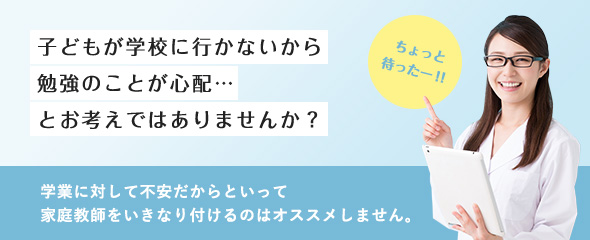【再掲載】「不登校」の定義は?そもそも…いったいどんな状態のこと?
こんにちは。
不登校支援センター横浜支部の庄子大貴(しょうじだいき)です。

私は過去に高校の教師として、不登校生徒専門のクラスを担当していた経験があります。そして、1つのクラスに集められた不登校の生徒達と関わる中で、私はまず最初にこんな疑問を抱きました。
それは「不登校って、いったい何だろう?」という疑問です。
今回は「不登校っていったい何だろう?」をテーマに話を進めていきます。

私は教師時代、生徒達に「あなたはどうして不登校になったの?」などを根掘り葉掘り聴くことはしませんでした。しかし、私と生徒との間に信頼関係が徐々に出来てくると、次第に生徒のほうから私に不登校になった経緯を話してくれるようになりました。
不登校になった理由としては、
・単純に学校に行きたくなった。面倒くさい。
・学校でいじめを受けていた。
・先生と折り合いがつかなかった。
・学校に行きたいけど、何故か行けなかった。
・部活動の先輩・後輩と折り合いがつかなかった。
・勉強に付いて行けなくなった。
・集団の中に居ると周囲の目線が気になって、行き辛くなった。
など、様々な不登校になった理由が、それぞれの生徒達にはありました。
ここで、文部科学省による「不登校の定義」を確認してみましょう。
「文部科学省は、「不登校」とは年間30日以上欠席した者のうち何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、児童生徒が登校しないあるいはしたくともできない状況にある者
ただし「病気」や「経済的理由」による者を除く」
と定義しています。
また、不登校状態が継続している理由として、平成13年度の文部科学省の調査においては、
・「不安など情緒的混乱」が26.1%、
・「複合(複合的な理由によりいずれの理由か主であるか決めがたい)が25.6%
・「無気力」が20.5%
といった割合となっていました。不登校状態が継続している理由の年代別の推移を見ると、近年は「複合(複合的な理由によりいずれの理由か主であるか決めがたい)」の割合が伸びていることが分かっているようです。
不登校の要因・背景の複合化や多様化の傾向が高まっているということでしょう。そして、中学校における「不登校状態が継続している理由」の1つには、「あそび・非行」があり、理由の中での高い割合を占めているようです。
また、文部科学省において不登校との関連として注目しているものに、学習障害(LD)、注意欠陥/多動性障害(ADHD)等があるようです。
・周囲との人間関係がうまく構築されない
・学習のつまづきが克服できない
もし、こういった状況が進んだ場合には、子どもが不登校に至ることも少なくはないと、文部科学省は新たな課題として指摘していました。
さらには、保護者による子どもの虐待等、子どもの登校を困難にするような事例も、不登校が継続する理由に含まれていました。文部科学省の見解として「個々の児童生徒が不登校となる背景にある要因や直接的なきっかけは様々で、要因や背景は特定できないことも多いという点に留意する必要がある」と述べていました。
以上が文部科学省による「不登校の定義」と、不登校が継続する理由のようです。
これらの文部科学省の不登校に対する見解は、【何らかの原因】が不登校へ繋がるという解釈によって定義付けされていると推測できるのではないでしょうか。
24年間変わらない!不登校が【原因論】として捉えられている現状

【何らかの原因】があるから、子どもは不登校になったという【原因論】に基づいた、文部科学省による「不登校の定義」ですが、平成13年から現在に至るまで24年間、変わること無くその解釈は使い続けられています。
しかし、時代が移り変わるのと同じように、不登校に対する見解や、対応方法はその時代に合った新しいものへと変容していくものではないでしょうか?
近年では「新型コロナウイルス」が不登校の原因の一つとして取り上げられていましたが、影響があったとしても、必ずの原因ではないと扱います。
私たち不登校支援センターは現在に至るまで、多くの不登校に悩まれるご家庭と接し、支援をしてきました。その中で多くの子どもと向き合い、それぞれの子どもにあった支援を行ってきた実績があります。そのデータを有効的に用いカウンセリング・コーチングに活かすからこそ、その時代に合った支援方法をご提供出来ると考えております。
私が過去に高校教師をしていたときに担当していた不登校クラスの生徒たちが挙げていた「不登校になった理由」が様々であったように、不登校の理由を挙げれば挙げるほど「複合的」になり、一概に「不登校とはこうである」と決めつけることはできませんよね。
また、理由を並べて見解を示していくだけでは、不登校の状態に対する根本的な解決にはならないのではないでしょうか?
根本的な解決を図るためにはその人の「目的」に注目する必要があります。
是非、不登校の子どもの心理に関してより知りたい方はお問合せ頂ければと思います。
皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。
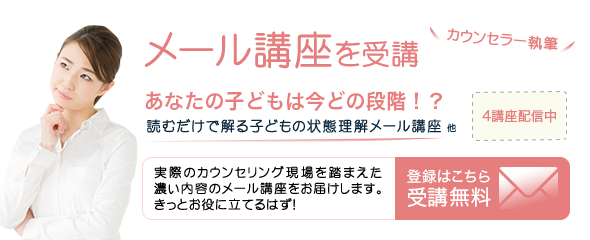

関連ワード: いじめ , やる気が出ない , 不登校 , 不登校の定義 , 人間関係 , 原因 , 学校 休む , 学習のつまずき , 横浜支部 , 無気力 , 目的 , 集団心理