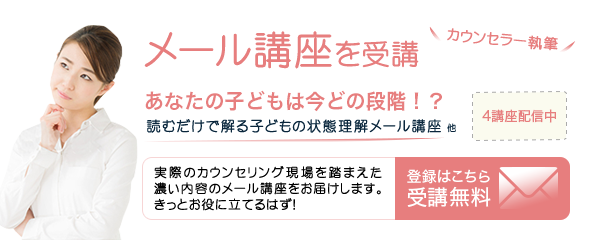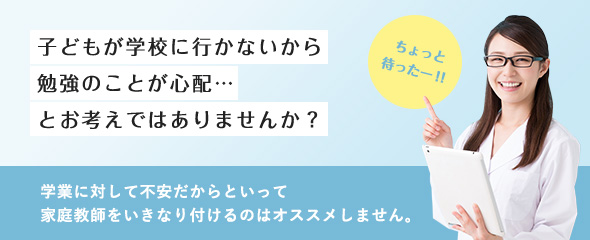子どもが学校に感じる不安②
こんにちは。
東京支部の椎名です。
秋の気配を感じ、今年一年が終わることをじわじわと感じる時期になってまいりましたね。この時期、私は「今年一年自分が何をしてきたか」「やろうと思って、できなかったこと、先延ばしにしたことはないか」と考えることがあります。
皆さんも今年中に終わらせたいこと、やらなくてはならないことなどあるでしょうか?

もしそれが終わらなかったとしたら、それは皆さんの一年間が忙しく、一日一日を過ごすことに精一杯だったということですよね。毎日を一生懸命過ごしている自分自身を労っていきましょう。
さて、前回のブログでは学校での人間関係づくりに不安を感じる理由や、不安を感じるお子さんの気持ちについてお話しました。
今回は、実際にそうした不安を抱えていたお子さんが不安と向き合っていった過程についてお話しようと思います。
~目を見て話すことができないAさんのお話~
Aさんが初めてカウンセリングに来たのは、小学校5年生の時でした。カウンセリングルームで対面したAさんは、机の上においてある観葉植物をじっと見ていました。今でもAさんの瞳が全く動かなかったこと、体に力がはいっていることが伝わってくる空気を覚えています。

Aさんは幼稚園生から小学校低学年まで、とても明るく活発で、お友達にも自分から積極的に話しかけるタイプの女の子だったそうです。公園に遊びに行こうとお友達を誘ったり、授業でも自ら手を挙げて発表するなど、自ら人と関わることが得意でした。
しかし、小学校3年生頃からお友達との距離感や、自然とできあがるグループに違和感を感じるようになったとのこと。「自分の発言が相手からどのように思われるか」「この子に嫌われたら、このグループにいられなくなるのではないか…」など気になることが増えるごとに、段々と相手の目を見て話すことができなくなり、自分から人に声をかけることも苦手になっていきました。
「誰にも嫌われたくないから、相手に合わせて疲れてしまう」「目を見て話すと、相手から自分がどんな風に思われているか想像して怖くなってしまう」と、Aさんは俯きながら話してくれました。
~相手の視線から感じる不安~
Aさんのように、相手の目を見て話すことに苦手意識がある方は珍しくありません。意識すれば目を見て話すことができるけれど、視線が合うと逸らしたくなってしまう、相手にじっと見られると緊張してしまう…そんな経験が皆さんにもあるかもしれません。

これは、相手から自分がどのように見られているだろうかということを不安視する気持ちが理由であったり、相手の表情から感情を読み取ることができてしまうため、「相手の感情に合わせてこちらが会話をしなくてはならない」と無意識のうちに感じて緊張感を強めてしまう、またこちらの感情を相手に見透かされるのではないかと戸惑い、不安に思うなど、様々な理由があります。
大人になる過程で、そうした自分の苦手に気が付き、自然と解消するための行動をとる方もいますが、Aさんのように幼い時期には「苦手」は「苦手」なまま認知され、解消するための行動をとることにも勇気が必要で難しく、気づくと人との関わりを避けたり、人がいる場所、視線を感じる場所に恐怖心を抱くようになるといったこともあります。
~Aさんが苦手と向き合ったきっかけ~
そんなAさんですが、今は中学生になり、お友達を誘って放課後お互いの家を行き来したり、推し活をしに出掛けたりと信頼できる関係性の中で楽しい時間を過ごしています。
Aさんが目を見て話し、お友達との関係性に不安を感じにくくなったきっかけ。それは英語検定の面接でした。
面接では面接官の目を見て会話をしなくてはいけません。
「少しでも自分に自信を持ちたい」と思い、勉強してきた英語検定に合格したかったAさんは「筆記試験は合格できると思うし、英会話も練習しているから英語で会話することもできると思う」「でも目を見て話すことだけが不安」「だから目を見て話す練習をしたい」と私に話してくれました。
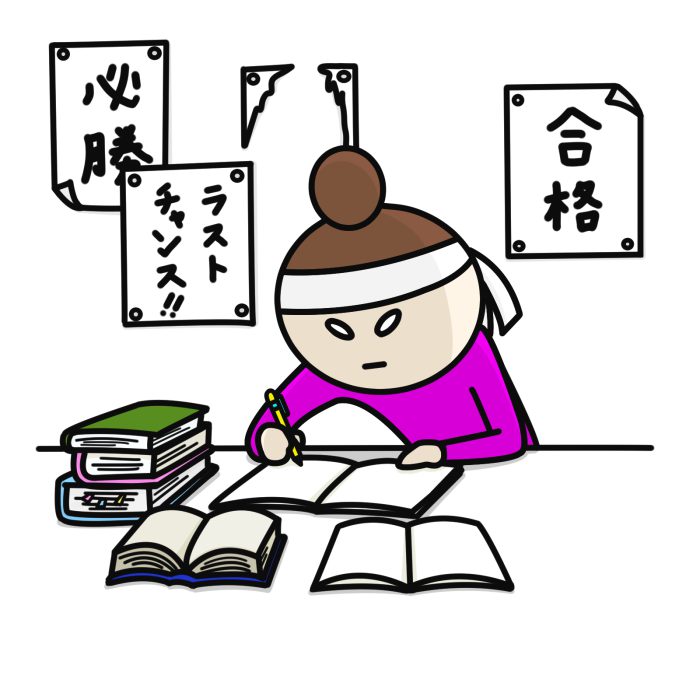
それからは、カウンセリングの中で相手の目を見なくともなんとなく首から上あたりを見ていれば視線が合っているように相手は感じること。
視線をずっと合わせなくとも、数秒視線が交差する程度でも、お互いに心が通じていると感じる瞬間が作れること、視線をどうしても合わせられない時には、相手の話を聞いていることを伝えるために、頷きや相槌を含めて会話することで印象が好転することなどを経験していただきました。
~苦手を克服するために必要なのは、主体的な課題意識~
Aさんが人の目を見て話すことができるようになったきっかけ、また人間関係を穏やかに営むことに対して自信をつけられたきっかけは、Aさん自身が「どうにかしたい」という主体的な課題意識を持たれたことです。
親御さんも、Aさんが以前のように友達を作り、目を見て話ができるようになったら…と望んでいました。しかしその親御さんとしての望みを押し付けることはなく、Aさんが自ら気づき、自分のために行動する時が来ることを見守っていました。
Aさんが自分のために勇気をもって行動するきっかけは、こうした周りの方の見守る力があってこそだったかもしれません。
さて、次回のブログではお子さんが感じる学校に対しての別の不安についてお話していきますね。


関連ワード: アイコンタクト , カウンセリング , コミュニケーション , ストレス , 不登校 , 不登校支援センター東京支部 , 目を見て話せない , 視線 , 視線が怖い