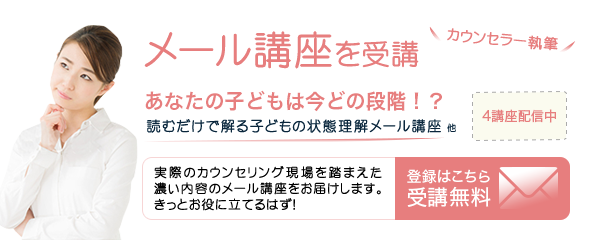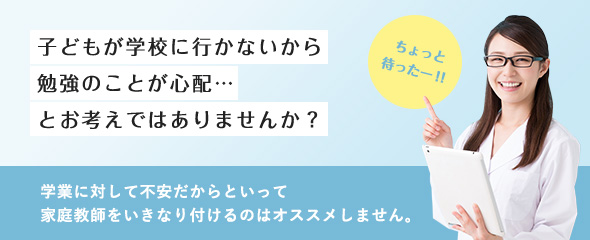勉強をしない子どもが変わる為に必要なこととは?②
こんにちは。
不登校支援センター 横浜支部の庄子大貴です。
今回は前回の続きである、「勉強をしない子どもが変わる為に必要なこととは?」を不登校支援をしている観点から、お話していければと思います。
勉強をしたくない子どもの理由とは?

こちらにご相談に来る親御さんや子どもからは勉強に対してのご相談も多くあります。勉強をさせたい「親」、勉強をしたくない「子」という関係は不登校に限らずあるのではないでしょうか?
私も塾講師や家庭教師、学校の教師をして来た経験もあり、勉強を教えることを仕事にして来ました。今でも、機会があれば、子ども達に勉強を教えております。
その中で、勉強をしたくない子どもの理由とは
・勉強する意味が分からない。
・勉強が難しいからやりたくない。
・勉強よりもやりたいことがあるからやりたいと思わない。
など、様々な理由が挙げられます。
この3つの理由でもそれぞれ子どもの主張に違いがあることにお気づきでしょうか?理由によって、対応の仕方や接し方も変わってきます。こちらについてお話をさせて頂ければと思います。
勉強が難しいからやりたくない。

子どもが勉強をしたくない理由の中の一つに「勉強が難しいからやりたくない」と発言するお子さんが居ます。親御さんに関わらず、教育関係者の方でもこの言葉を言われると困惑されると思います。
「それは必要なことだから」と諭すことも多いのではないでしょうか?
実際、勉強が難しくなる時期として、「小1」、「中1」が有名です。
小学校1年生に関しては幼稚園・保育園から上がり、小学生になる為、「勉強」の概念が急に入ってくる感覚です。その上、椅子に座って授業を受け、静かにすることが前提となる為、違った世界に映っていると思います。そこに「勉強」をするとなると、子どもによってはキャパオーバーになり、ストレスが大きくなる場合もあります。
中学校1年生に関しては小学校の勉強から科目数が増えたり、勉強の概念が変化したりする為、環境の変化についていくことが難しいと感じる傾向にあります。特に「算数」から「数学」は小学校までの常識が覆る感覚になる子が多い為、アレルギーに感じる子どもが多いと考えられます。
「勉強が難しいからやりたくない」子どもへのアプローチ

では、この様な子どもに対してどうアプローチをすればよいでしょうか?何かに無理矢理結びつける、例えば「将来の為」、だと子どもの納得は得られないことが多いです。納得を得ない状態で言うことを聴く子どももいますが、聴かない子どもいます。その為、勉強に対して「興味・関心・意欲」を持たせる取り組みが必要になります。
現在の子どもは五感を使った学びが少ないように思います。その上で、デジタルに適応しなければならない時代でもあり、とても不自由である捉え方も出来ます。
ただ、人として大切な感覚は今も昔も変わらない為、五感を活かすことが前提として大切です。勉強も意味がある、面白いと思うことが大切であり、人生の経験値が左右するものです。「意味が無い」と切り捨てる考え方が増えた現代ですが、「意味がある」と感じる為には経験からの紐づけが必要です。
勉強も「難しいから」と言っている場合、一旦離れて別の学びをアプローチすることで「必要」と感じることもあると思います。
つまり、「難しいけど頑張らせる」は子どもによっては難しい方法であり、五感を使った他のことを挑戦させることが効果的であると言えます。是非、子どもの時に出来る感動に挑戦してみてください。
次回も「勉強をしない子どもが変わる為に必要なこととは?」について、お話をしたいと思いますので、是非ご覧下さい。
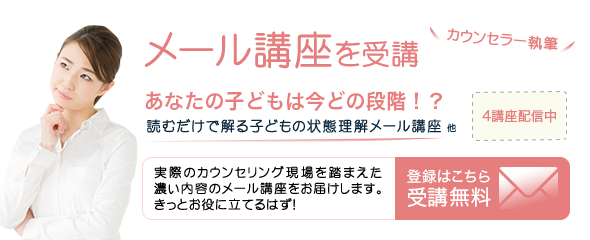

関連ワード: デジタル , 中1ギャップ , 五感 , 勉強 , 勉強が難しいからやりたくない , 勉強するよりもやりたいことがある , 勉強する意味が分からない , 勉強の意味が分からない , 小1の壁